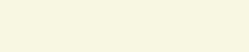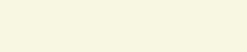梅若は元は梅津といい、京都梅津の豪族で橘諸兄を祖としていると言われている。梅若と姓を改めるのは1481年梅若太夫景久が後土御門天皇に召され、宮中で「芦刈」を演能の折りに、「若」の一字を賜ったことにより、梅若姓を名乗ることになる。以後梅若家においては、「芦刈」の曲は特別な意味を持つ曲である。
梅若家は織田信長の寵愛を受け、たびたび勧進能を催す折、勧進元を賜っていた。丹波城主明智光秀の家臣であったことや、京都に所領が在ったために、江戸時代に入って武家式楽の四座制定の頃には江戸に出て行くことが出来ず、結局観世家のツレ家として入ることになる。梅若家は座の家元にはならなかったが、徳川家や宮家の寵愛を受け勧進能の際などにはシテを勤める"太夫"と称され、家元並みの扱いを受け、禄も観世宗家からではなく、徳川家より直接受けていたようである。
明治維新により武家階級消滅の結果、それぞれの家は地方へ分散したが、梅若家と観世分家の銕之丞家は江戸にとどまり財政的にも窮しながらも演能を続ける。
欧米視察より芸術文化の大切さを痛感した岩倉具視は、芸術文化復興の一つとして能楽に着目し、華族能を催していく。
各家元が東京へ復帰するきっかけとなったのは、岩倉邸で梅若六郎(初代実)が奉った天覧能である。こうして梅若家も能楽界も三井家や三菱の岩崎家などの財閥の庇護の下に再び隆盛を極めることになる。
初代万三郎は初の日本芸術会員になり、1937年には初代実が日本芸術院会員となり、兄弟共に会員となる。
第二次大戦の折には、他家も被ったように梅若家も多くの由緒ある面や装束を空襲で失った。
1955年には二代実が芸術院会員となり、60年には現在の東中野に梅若能楽学院会館を完成させ、合わせて日本唯一の能楽各種学校として、梅若能楽学院を開校した。
現在の梅若六郎は五十六世である。
梅若家は織田信長の寵愛を受け、たびたび勧進能を催す折、勧進元を賜っていた。丹波城主明智光秀の家臣であったことや、京都に所領が在ったために、江戸時代に入って武家式楽の四座制定の頃には江戸に出て行くことが出来ず、結局観世家のツレ家として入ることになる。梅若家は座の家元にはならなかったが、徳川家や宮家の寵愛を受け勧進能の際などにはシテを勤める"太夫"と称され、家元並みの扱いを受け、禄も観世宗家からではなく、徳川家より直接受けていたようである。
明治維新により武家階級消滅の結果、それぞれの家は地方へ分散したが、梅若家と観世分家の銕之丞家は江戸にとどまり財政的にも窮しながらも演能を続ける。
欧米視察より芸術文化の大切さを痛感した岩倉具視は、芸術文化復興の一つとして能楽に着目し、華族能を催していく。
各家元が東京へ復帰するきっかけとなったのは、岩倉邸で梅若六郎(初代実)が奉った天覧能である。こうして梅若家も能楽界も三井家や三菱の岩崎家などの財閥の庇護の下に再び隆盛を極めることになる。
初代万三郎は初の日本芸術会員になり、1937年には初代実が日本芸術院会員となり、兄弟共に会員となる。
第二次大戦の折には、他家も被ったように梅若家も多くの由緒ある面や装束を空襲で失った。
1955年には二代実が芸術院会員となり、60年には現在の東中野に梅若能楽学院会館を完成させ、合わせて日本唯一の能楽各種学校として、梅若能楽学院を開校した。
現在の梅若六郎は五十六世である。